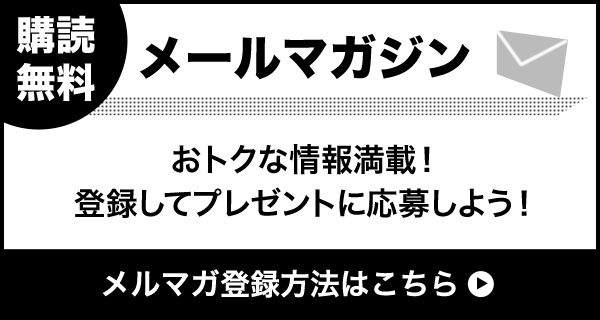ロータスクラブが運営するクルマとあなたを繋ぐ街「ロータスタウン」
みらいのくるまの「ただいまのところ」情報
日本EVクラブ主催『第24回 日本EVフェスティバル』ルポ② 小っちゃくて静かなのに迫力満点のレース!
2018年11月22日更新

ここからは、フェスティバルで行われた各レースの模様をルポする。
午前中に実施された電気カート(Electric Racing Kart=ERK)のレースや市販EVによるタイムアタックは、ほぼ無音ながらも迫力は満点だった!
〈ERK30分ディスタンスチャレンジ〉
スピード感溢れるバトルを展開
午前10時、〈ERK30分ディスタンスチャレンジ〉がはじまった。
これは、参加する各チームが手づくりしたERKで30分間にどれだけ多く周回できるかを競う耐久レース。ドライバーは2人以上で、5回のピットイン(ドライバー交替)が義務付けられている。
同じ30分のなかで、48Vの鉛電池搭載のERK-1クラス、72Vの鉛電池搭載のERK-2クラス、リチウムイオン電池搭載のERKリチウムイオン電池クラスという3つのクラスごとで順位が争われた。
エントリーチームは、仲間が集まったチームのほかに、自動車大学校や大学のチーム、あるいは東京マツダEVプロジェクトチームやDENSOチームなどの社会人チームまでさまざま。女子チームも見受けられる。


会場のコース1000には、隣にあるコース2000での二輪レースのエンジン音が響いていたが、こちらのレース自体はほとんど無音といっていいほどの静けさのなかで行われた。
ただ、だからといって迫力がないわけではなかった。舘内代表いわく「1周のラップタイムは125ccのレーシングバイクと同等かそれ以上」なのだそうで、たしかにスピード感溢れるバトルが至る所で繰り広げられていた。観客たちからの「おおっ」との感嘆はその証左といえる。短い動画を添付したので、熱いレースの一端をぜひご覧いただきたい。
各クラスの優勝チームと周回数は以下のとおり。
ERK-1:『Enersys Feat.あわネコレーシング』28周
ERK-2:『ミツバ』31周
ERKリチウム:『トヨタ東京自動車大学校 自動車研究部』36周
ERKリチウムイオン電池クラスで、2位を5周も離してぶっちぎりの優勝を果たした『トヨタ東自大 自研部』のドライバーは、勝因について「容量の大きいバッテリーを積んだことと、熱をもつと性能が落ちるモーターを風が当たりやすいところに設置したこと。あともう一つは、ドライバーの力量かな(笑)」と語っている。
〈何でもEVデモ走行/ベンチャーデモ走行〉
さまざまなる意匠で駆け抜けるEVたち
午前11時30分からは〈何でもEVデモ走行/ベンチャーデモ走行〉が実施された。
〈何でもEVデモ走行〉は、学生などが創意工夫してつくったオリジナルのEVによるデモンストレーション走行で、さまざまなタイプのEVがサーキットのコース上を走り抜けた。
このなかでもっとも目を惹いたのは鹿沼高校物理部の生徒たちがつくった折り畳み式立ち乗り型EVのKPCEV-07。後に行われた表彰式では「チャレンジ達成賞」を授賞している。

折り畳み式立ち乗り型EVのKPCEV-07。試験中の生徒たちに代わって、先生がドライブした。

神奈川大学のKF-04EV。第16回全日本学生フォーミュラ大会に出場した車両。
〈ベンチャーEVデモ走行〉は、コンバートEV製作などを行っているベンチャー企業が手がけたクルマのデモンストレーション走行。この中では、オズモータースが手がけたビートルのコンバートEVの存在感と走りが際立っていた。
舘内代表が「バッテリーをはじめ、多くのリユース部品を使いながらも、非常にきれいにコンバージョンされている。もちろん公道の走行もOK。コンバートEVをつくりたいと思っている皆さんには、ぜひこれを参考にしていただきたいですね」と述べているように、その完成度はバツグンだった。コンバートEVの製作はお金も時間も労力もかかるといわれているが、「こだわりのある古いクルマを美しいEVとして蘇らせたい」と夢見る人にとっては垂涎の1台といえるだろう。


〈メーカー製EVオーナーズ・タイムアタック〉
i-MiEVが奇跡的なタイムを記録
午前11時50分からは〈メーカー製EVオーナーズ・タイムアタック〉が行われた。
これは、一般に販売されているノーマルEVのオーナーたちによる競技。速さではなく、1周をいかに基準タイムの1分に近いタイムで走れるかを競う・・・というユニークな競技である。
レースは意外にも興奮の展開となった。
前半で、日産リーフのオーナーが1分0秒315という驚異的なタイムを記録し、優勝まちがいなしと思われた。
だが、最後に走った三菱自動車i-MiEVのオーナーがそれをさらに上回る1分0秒117という奇跡的なタイムを叩きだし、見事に優勝をさらっていったのだ。
三菱自動車MINICAB-MiEVトラックの走行シーンでは、ほのぼのとした雰囲気がレースを包んだりもしたが、この最後のシーンで観客たちは大いに沸いたのであった。

優勝した三菱自動車i-MiEV

惜しくも優勝を逃した日産リーフ
とにかく1分に迫ることコンマ何秒というタイムを出すというのはすごい。
日頃からEVを運転している人はリニアな加速をするEVの特性を十二分に理解していて、それを自在にコントロールできるドライビングテクニックを身につけているということの証左と言えようか。 (続く 文:みらいのくるま取材班)

サーキットを走るMINICAB-MiEVトラック
1 アクセル全開で楽しみながらCO₂の削減を!
2 小っちゃくて静かなのに迫力満点のレース!
3 新しいレース観をつくりだすEV特有の走り!
4 エンジン車とEVの両方を愛する新人類の登場!
関連キーワード
あわせて読みたい
-
みらいのくるまの「ただいまのところ」情報
次世代エコカー勉強会〈4時限目〉プラグイ…
『次世代エコカー勉強会』は未来のクルマや新しいカーライフを研究するコーナー。4時限目のテーマは「プラグインハイブリッドカー(PHV/PHEV)」。その電気自動車…
2016.03.30更新
-
みらいのくるまの「ただいまのところ」情報
EVキーマンに聞く/CHAdeMO協議会…
CHAdeMO(チャデモ)協議会は、EVをはじめとする電動車のための急速充電器の規格を開発・管理する団体で、ロータスクラブもその一員となっている。2010年、ゼ…
2020.03.19更新
-
みらいのくるまの「ただいまのところ」情報
第26回 日本EVフェスティバル レポー…
冷たい雨が降る中、東京の東京国際交流館を舞台に約6時間にわたって行われた第26回日本EVフェスティバル。午後の〈気候非常事態宣言EVシンポジウム〉の終盤に行…
2021.01.14更新
-
みらいのくるまの「ただいまのところ」情報
2021全日本EVグランプリシリーズ 第…
今季スポット参戦ながら、その速さで周囲をざわつかせている女性ドライバーの今橋彩佳選手。なぜ、そんなに速いのか?いったいどんな経歴の選手なのか?レースが終わっ…
2021.08.27更新
-
みらいのくるまの「ただいまのところ」情報
BookReview(29)『2035年…
衝撃的なタイトルは事実を端的に表しただけ『2035年「ガソリン車」消滅』というタイトルは、一見すると危機感を煽っているように思える。だが、これは煽りでも何…
2021.09.08更新
-
みらいのくるまの「ただいまのところ」情報
みらいのくるまルポ~『東京ロボット』:E…
IT企業がEV開発に挑戦いま、世界中で自動車メーカー以外の企業がEV(電気自動車)の開発・販売に積極的に乗りだしている。それは日本においても同様。9月29日…
2017.11.02更新


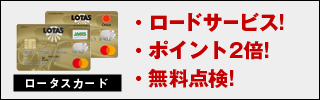
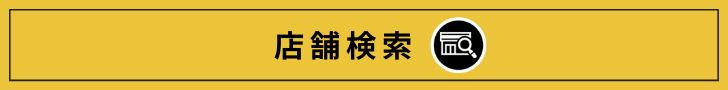
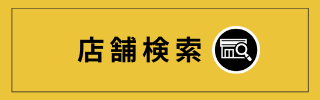


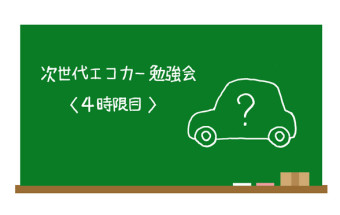



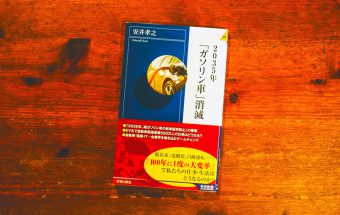

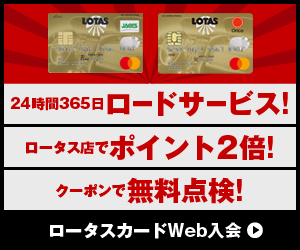




![Vol.1 デート帰りの深夜0時に、民家の塀をこすっちゃった。さて、どうすればいい?[前編]](/managed/wp-content/uploads/2015/10/1143d85a60cc76b8894376be0504aa15-100x65.jpg)