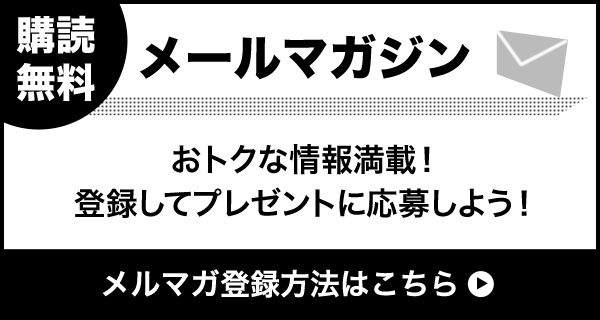ロータスクラブが運営するクルマとあなたを繋ぐ街「ロータスタウン」
みらいのくるまの「ただいまのところ」情報
BookReview ⑦『自動車会社が消える日』~日本のメーカーのEV化はまあまあだが、自動運転化はイマイチ!
2018年5月15日更新
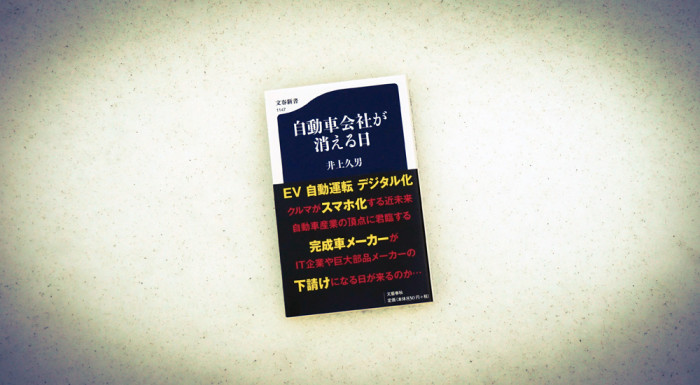
刺激的なタイトルには裏づけがある
『自動車会社が消える日』とは、なかなか刺激的なタイトルだ。
いったい、どういうつもりでこんなタイトルをつけたのだろうか?
著者は「はじめに」でこう書いている。
“今、自動車産業の大きなパラダイムシフトが進みつつある。本格的な自動車産業が誕生したのは100年以上前の1908年。アメリカでヘンリー・フォードが「T型フォード」を大量生産して、販売をはじめたときだが、それ以来の劇的な変化が起きているのだ。”
“ところが日本の自動車産業は、そうした変化に対応できているようには見えない。受け身に回って外国企業や新規参入組から攻められつづけていると言った方が正確かもしれない。しかも一部の経営者はそうした現実から目を逸らそうとしているようにさえ見える。それこそが危機なのだ。”
つまり、世界的にEV化、自動運転化の動きが急となっている現在、日本の自動車メーカーの対応は遅すぎるし、かつ消極的であり、このままでは凋落していく可能性が大だと警鐘を鳴らしているのである。
著者は、朝日新聞の記者時代から二十数年にもわたって自動車業界を取材しつづけており、一般の人が知り得ない各メーカーの開発情報はもちろん、経営事情にまで通じている。しかも、世界の自動車業界の動向も広く深く知り尽くしている。その著者が言うのだから、単に人の気を惹くための煽りとは思えない。刺激的なタイトルにも、それなりの裏づけがあるようだ。
欧米勢に握られつつある
自動運転のデファクト・スタンダード
実際、第1章「スマホ化するクルマ」を読むと、たしかに自動運転に関する動きは遅れがちかもしれないという印象を強くする。
たとえば、アメリカのシリコンバレーでは世界各国のIT企業や部品メーカーなどが参加する形で自動運転技術の標準化が進められているということだが、日本の自動車メーカーなどは、そこからはまったくの蚊帳の外におかれているという。
“自動運転を支える技術開発でも日本は大きく出遅れ、デファクト・スタンダードは欧米勢に握られつつあるのが現状だ。”
“このままではいずれ自動運転に関するOSなどの基本技術は「シリコンバレー」に握られ、自動車メーカーは「箱」だけを造る時代が来るかもしれない。”
懸念されることは、まだある。
日本では自動運転は、もし自動運転が困難になったときにドライバーが運転に関与するレベル3までが現実的という考え方が主流であるところ、ドイツやアメリカでは不完全な人間が関与するレベル3よりも完全自動運転のレベル4のほう安全で現実的であるという議論が出始めていて、実際に各メーカーはその方向で開発を進めているというのだ。
“人工知能では、こうしたリスクへの対応も可能になりつつある。日本メーカーがこつこつ積み上げてきたデータに代わって、ビッグデータから人工知能が判断してアルゴリズムを構築できてしまうからだ。”
“しかし、日本の大企業の経営者はこうした大胆な発想になかなか付いていけず、現実を直視しない傾向にある。”
日本に住んでいるわれわれは、完全自動運転の実現はまだまだ先のことだと思っているところがあるわけだが、それはもしかしたら日本の自動車メーカーが醸しているムードを素直に受け入れてしまっているからなのだろうか?
もしかしたら、それは思い違いなのかもしれない。
日本のメーカーは
EVでは決して出遅れてはいない
では、EV化についてはどうか。
やはり日本のメーカーは遅れているのだろうか?
じつは本全体をとおして、著者はこのことについては自動運転化に比べると批判的ではない。それどころか、ときにメーカー各社の独自の取り組みを褒め称えてさえいる。
たとえば、現在、エンジン車ならびにディーゼルエンジン車の開発と販売に大きな力を注いでいるマツダの今後のEV車(PHEV)開発への取り組みを、このように紹介している。
“マツダの小飼社長も、「クルマのパワートレイン(動力源)はマルチソリューションの時代」と語る。マツダは19年に発売する予定のEV開発にも力が入っている。--中略-- 「コモンアーキテクチャー」や「モデルベース開発」を駆使して、独創的なEVを出すといわれている。”
“このEVで、マツダは看板技術だったロータリーエンジンを復活させる計画だ。EVは電池が切れた際に近くに充電設備がないと困る。それをカバーするために、発電機として小型ロータリーエンジンを搭載するのだ。”
“マツダでは内燃機関の技術を徹底的に磨いたうえで、その上に少しずつ電動化技術を積み上げ、その最上位にEVなどを置いている。これは2000年代半ばから決めている戦略だ。だから「マツダがEVで遅れている」という見方は皮相的なのだ。”
よく考えれば、世界初のEV市販車は三菱自動車からでている。いま、世界で一番売れているEVは日産のリーフである。マツダをはじめ、まだピュアEVを商品化できていないメーカーが複数あるが、著者は日本の自動車メーカーの技術力は、EV化については整っているという見解なのだろう。
いずれにせよ、この本で著者が危惧するのはあくまで自動運転化のことであり、それが『自動車会社が消える日』という過激なタイトルとなったようだ。
昨年来、テレビなどのマスメディアは「EV化」へのシフトを大きく報じているが、著者が提起するようにパラダイムシフトの力点は「自動運転化」であるのかもしれない。(文:みらいのくるま取材班)
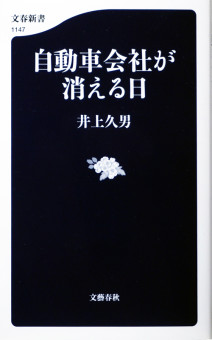
『自動車会社が消える日』
・2017年11月20日発行
・著者:井上久男
・発行:文藝春秋
・価格:830円+税
関連キーワード
あわせて読みたい
-
みらいのくるまの「ただいまのところ」情報
BookReview(47)『2024年…
ロータスクラブの提携企業である三菱自動車は、2023年5月に軽スーパーハイトワゴンのデリカミニを発売した。このデリカミニ、前身とされるeKクロススペースからデ…
2024.01.11更新
-
みらいのくるまの「ただいまのところ」情報
ALL JAPAN EV-GP SERI…
ALLJAPANEV-GPSERIESの王者を生み出してきたTeamTAISANの千葉泰常代表が、6月7日に逝去された。6月29日(土)に袖ヶ浦フォレ…
2024.07.11更新
-
みらいのくるまの「ただいまのところ」情報
次世代エコカー勉強会〈6時限目〉「自動運…
夢のクルマであったはずの自動運転車が、現実のものとなる気配が濃厚になってきた。ということで取り急ぎ勉強会をスタート。自動運転の「ただいまのところ」をシリーズで追…
2016.06.14更新
-
みらいのくるまの「ただいまのところ」情報
JAPAN MOBILITY SHOW …
三菱自動車とスズキは、ロータスクラブと提携している自動車メーカーだ。これまで三菱はオフロードの走りに定評のあるクルマを数々発売し、スズキは軽自動車を中心に身近…
2023.11.14更新
-
みらいのくるまの「ただいまのところ」情報
「東京モーターショー2017」ルポ(2)…
第45回東京モーターショー2017のルポ第二弾では、すでにEVを発売済みの日産自動車と、二つの海外主要メーカーのEVコンセプトカーの概要について見ていきたい。…
2017.11.09更新
-
みらいのくるまの「ただいまのところ」情報
2021全日本EVグランプリシリーズ 第…
予選時ほどではないが、雨は依然としてポツポツと降っていた。コース上は全面にわたって黒く濡れ、場所によっては水たまりもできていた。2021全日本EVグランプリシ…
2021.08.27更新


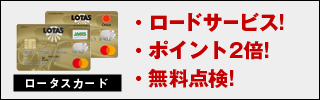
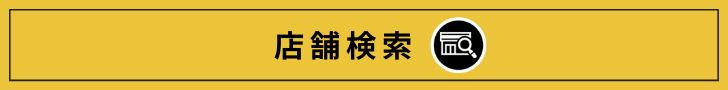
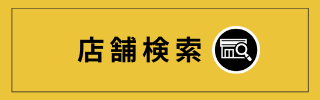


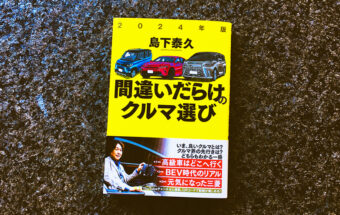

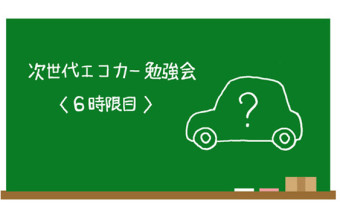



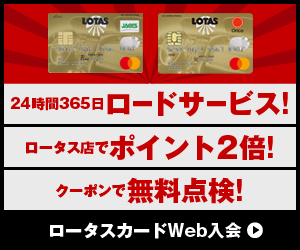




![Vol.1 デート帰りの深夜0時に、民家の塀をこすっちゃった。さて、どうすればいい?[前編]](/managed/wp-content/uploads/2015/10/1143d85a60cc76b8894376be0504aa15-100x65.jpg)